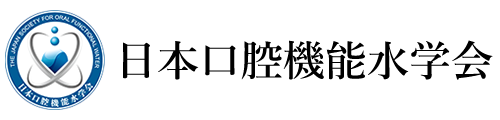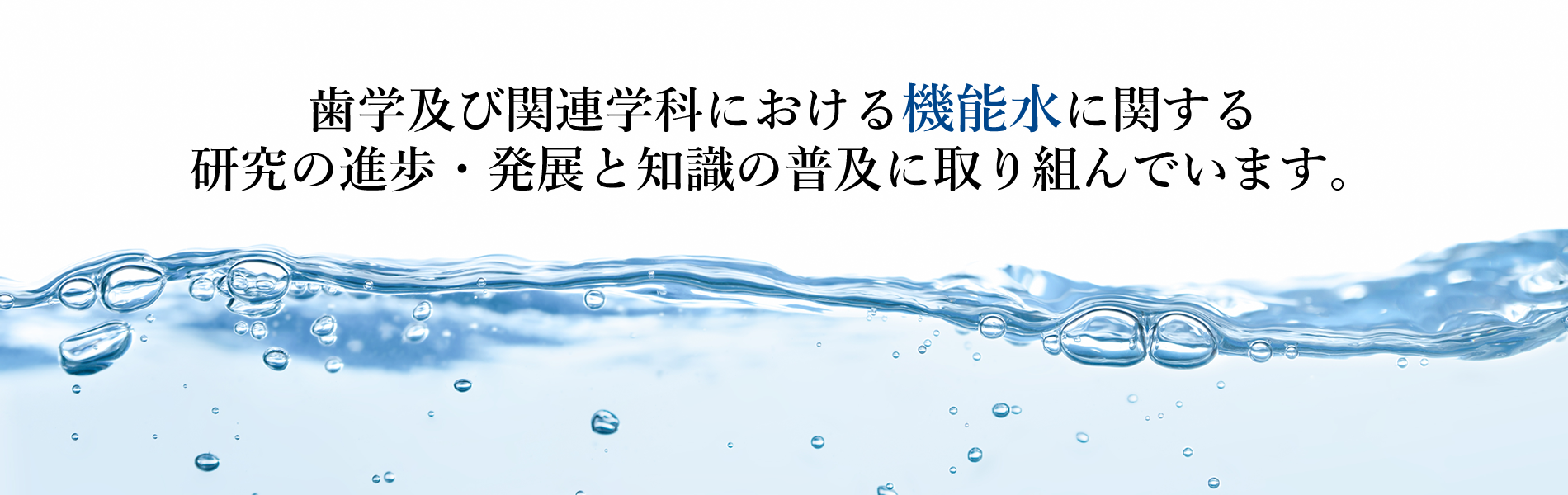日本口腔機能水学会とは
日本口腔機能水学会は昭和大学、日本大学、日本歯科大学等が中心となって東京、神奈川、埼玉、千葉の各歯科医師会の協力を得て1994年強電解水歯科領域研究会として発足しました。研究会設立の目的は、強電解水の使用法、作用メカニズム、水自体の構造や物性を解明することです。現在会員数は約200名。2000年3月に第1回日本口腔機能水学会学術大会を開催して以降、毎年学術大会を開催しております。
会長挨拶
この度、2025年(令和7年)4月より、西田哲也先生の後任として日本口腔機能水学会の会長を仰せつかりました日本大学歯学部 病理学講座の浅野正岳と申します。本学会は、アクア酸化水研究会および強電解水歯科領域研究会(1994年:平成6年)を前身とし、ヒトの体の2/3を占め、生命維持にとって必要不可欠な水に関する学術研究を推進する学術団体です。多くの研究者の30年を超える取り組みによって、現在では機能水は「人為的な処理によって再現性のある有用な機能を獲得した水溶液の中,処理と機能に関して科学的根拠が明らかにされたもの及びされようとしているもの」と定義されるに至りました(機能水研究振興財団)。機能水には、アルカリイオン水、強酸性電解水、薇酸性電解水など様々な種類のものが存在しますが、本学会では、これらを口腔領域のみならず全身の疾病の改善、予防、健康増進に役立てるための様々な研究活動を支援したいと考えています。
私自身の本学会とのかかわりは、10年ほど前に遡ります。当時、本学の歯周病学講座の伊藤公一教授のご指導の下、大学院生と共に培養細胞に酸性電解水を作用させるという実験を行っていたころです。この実験によって、細胞が自身に迫った危機的状況を周囲の細胞に伝達するdanger-associated molecular patterns (DAMPs)といわれる分子が、細胞から放出される現象に出会い、その成果を本学会において発表したのが最初です。以降今日までDMAPsの一種であるinterleukin-1α(IL-1α)という分子に着目した研究を行ってきました。今では、引退までの残りの期間を、IL-1α研究に捧げる覚悟です。こうしたことから、機能水は私の研究の道筋を定めてくれた非常に重要なものであったと考えています。
しかし機能水には、未だ解明されていない多くの問題が潜んでおり、これらを解き明かすのは容易なことではありません。これらの問題に果敢に取り組み、その成果をより多くの研究者に報告して頂きたいとの思いから、今後益々水に関する研究活動を推進してまいりたいと考えています。会員ならびに関係の皆様のご理解とご協力を引き続き賜りたく、心よりお願い申し上げる次第です。